<5>
じり、と俺は数センチ彼らに近づいた。
「おっと、人質がどうなってもよろしいんですか?」
ぐっとナイフが兄の喉に食い込む。それ以上押し付けたらぷっつりと切れてしまうだろうくらいに。
「さぁ、じっとしていてください、マシアス従兄様。最後の仕上げをしましょう」
ナイフを突きつけたまま、ジルベールは片手で器用に、テーブルの上にグラスを二つ並べ、酒を注いだ。そしてそのうちの一つに、何かの粉を振り入れた。
彼は片手で、そのグラスを持ち上げた。
兄が俄かに抵抗しようと身動ぎした。
「暴れると刺さりますよ、エドガー従兄様」
グラスは、身動きできないでいた俺の鼻先に突きつけられた。
「飲んでください」
彼は嫌な笑みを浮かべた表情で言った。
「飲まなければ、貴方の兄上は酷いことになりますよ」
「何を入れた」
「大丈夫です、苦しむことはありませんよ。兄が弟を殺すのに、わざわざ苦しむような毒薬を選ぶことはないでしょうから」
それで思い出したのは、フランシス叔父が処刑になるとき、父がどうしてもと言って、絞首ではなく毒殺になったのだという話だった。
苦しませたくないと父が言ったのだと、後から聞いた。
――こんなのは嫌だった。どうしても認められなかった。
奴の手を振りほどいて逃げてくれればいいのにと、俺は兄を見た。彼は目を閉じていて、俺を見ていなかった。
しかし、その顔は絶望しきったそれではなかった。兄は何かを考えているらしかった。
時間を稼がねば。
「こんなことをして、叔父上が喜ぶと思っているのか?」
我ながら陳腐な台詞だと思ったが、他に何も思い浮かばなかった俺はそう言った。
兄が、ちらりと目を開いて俺を見た。
「もちろんですとも」
「……そりゃ、叔父上は親父を殺そうとしたけれど、でも、だからってお前がこんな風に罪を犯すことを、喜びはしないと思うぞ」
しかし、彼はふふ、と笑っただけだった。
「そんなにこの国の玉座が欲しいのか?」
「もちろん」
「それなら、そんなものくれてやるさ。命を奪われなくたって」
「それは不可能です」
ジルベールは目を細めた。
「罪人の子は罪人。貴方々が生きている限り、それは不可能なのですよ、マシアス従兄様。それでも、みな死んでしまえば、私の血筋に頼るしかない。後悔するでしょうね、女好きの貴方が何故結婚して子を成さなかったのか、エドガー従兄様」
「私の子を危険に晒さずにすんで良かったさ」
兄は目を開いた。今度は酷く絶望した表情をしていた。そして、彼の目は俺に向けられた。兄の目は静かに、俺に伝えていた。
兄は、ずっと従弟を助ける手立てはないかと考えていたのだ。
間を計ることも、合図も必要なかった。
一瞬の隙を――最も、彼は兄がされるがままになっているので、隙だらけではあった――突いて、兄が彼の利き腕を取る。それと同時に俺は背後に回りこみ、動きを封じた。
今から思えば、二人対一人ではあまりに不利だった。
兄が右手に握られていたナイフを叩き落し、左手のグラスが激しいクラッシュ音と共に床で砕け散った。
「ジルベール、もうお終いにしよう」
兄は言った。
「私は、君をこんな風にしたくはなかった」
ジルベールが僅かに腕を振ったが、俺はますますギリギリと締め上げた。
「あの日、君を逃がしたあの時から、いつかこういう日が来るんじゃないかと思っていた。どうしてかは分からない。君は何も知らなかったし、知る術もないはずだった。それでも、私にはいつか君がここにきて、こんな風に私を亡き者にしようとするのが分かっていたんだ。そして、私は愕然とした。君を救う手立ては、君を逃がした時点で何もなくなっていた」
誰かが廊下を駆けてくる音が響いた。
「それが、私の犯した重大な罪だったのだと、今はっきり自覚したよ。済まない」
ジルベールは、キッと兄を睨んだ。
「私は貴方を許さない」
「それで結構だ」
兄は立ち上がった。
「いつまでも、恨んでいてくれていい」
喉元にやっていた手を離す。
ぽたり、と床に血滴が落ち、一瞬俺は我を忘れた。
「ジルベール!」
本当に一瞬のことだった。あまりに素早くて、我に返る時間を与えられなかった。
さっと身を翻し、彼は起き上がると、さっき俺が開け放った窓と反対側の窓の淵に手をかけた。
「いけない」
兄が悲痛な声で叫んだ。
「ダメだ、そこは――!」
身体が宙に飛び出した直後、俺は彼の腕を掴んで引き止めた。肩が軋んだ音を立てた。
「離せ!」
「それじゃ何の解決にもならないだろ!」
20メートル下には、一面石畳の通路が広がっていた。物音を聞きつけたのだろう、誰かがこちらを見上げて悲鳴を上げた。
「私は負けたんだ。結局、13年経ってもあの人には勝てなかった」
「ジルベール!」
手を離そうと、振り回す。
「父さまはいつも言っていた! 従兄に負けるな、勝って、いつかお前が王の座を得るのだと!」
兄がカーテンに凭れ、一瞬震えた気がして俺は目を上げた。
その隙に、更に身体が窓の外へと引っ張られる。
背中越しに兄の手が伸び、ジルベールの手に触れようとした。
「触るな!」
どうして彼が小柄なままいてくれなかったのか、俺は呪った。重みに引きずられ、どんどん身体が引っ張られる。
「マッシュ」
兄は手を伸ばすのを止め、俺の身体を支えた。
「離すんじゃないぞ」
「分かってる」
「あんたに勝つのは簡単だったさ、マシアス。あんたは病弱で、頭も良い方じゃなかった。道場に来た時だって、人の何回りも身体が小さくて、俺は心の中であんたを馬鹿にしたものさ!」
彼は更に腕を揺さぶった。
「それなのに、あんたはどんどん頭角を現して、俺は追われるように逃げるしかなかった。あんたのせいだ!」
ギリギリと、腕が食い込む。
「俺は、あんたたち二人に勝てなくなった! 絶望したんだ!」
「エドガー様!」
バンッとドアが開いた音がし、誰かが駆け込んできたのを俺は察した。
「ご無事ですか?」
「すぐに下へ! ここから引き上げるのは無理だ」
兄が振り向いて叫んだ。しかし、そう命じられた相手は何を言われているのか俄かには理解できていないようだった。
「それなら、殺すしかないと思った。父さまの敵を討つしかないと思ったさ!」
苦しい。胸が重みに耐えたまま、窓の桟に押し付けられているからだけじゃない。
どうして、こんな風に憎み合うことしか出来なかった?
あの二人は、兄弟だったのに。
彼の、俺が掴んでいたのとは逆の手が不意に持ち上げられた。
「ジルベール!」
背中越しに状況を窺ったままだった兄が、身を乗り出して叫んだ。
しかし、彼はそれに反して、何かを口に含んだ。
「あ」
それは、さっき。
急に腕の重みが増し、俺は呆然として手を離してしまった。
こちらを見上げて右往左往していた人々が、一斉に悲鳴を上げた。
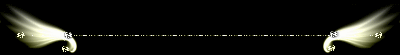
その日も、燃え滾った太陽が砂を照り付けていた。
蜃気楼が砂の丘の向こうに立ち昇り、何もかもが暑さに溺れ、ぼんやりとぼやけて見えた。
そうだ、今年の夏は酷く暑いではないか。
そう言った兄の言葉を、今更ながら俺は思い出していた。
「一つだけ、分からないことがあるんだ」
全てが済んだ後、ふと兄はそう言った。
「分からないこと?」
聞き返すと、兄は小さく頷いた。
「誰が彼に真実を伝えたのか」
俺たちは、しばらく互いの目を見つめていた。
「あのことを知っているのは、ごく僅かな人間のはずだ」
兄の言葉に、俺は小さく頷いた。そのまま、二人とも何も言わずにそれぞれ床と天井を見ていた。
王の間に、ひどく静かな時が流れる。
「よっす」
不意に聞き馴染んだ声がして、俺は振り向いた。
「ロック!」
「やぁ、ご苦労さん。例の件、見つかったか?」
ロックはにっと笑うと、背中に隠れていた子供を引っ張り出した。
何事かと、思わず目を瞠る。
――ああ、そうか。
見紛うはずがなかった。その子は、彼の小さな頃に良く似ていた。
「ジルベールの息子だ。ロックに頼んで探してもらっていたんだ」
兄が言う。子供は六つか七つかという年頃で、怖々と俺たちを見上げていた。
「城で引き取ろうと思うんだ。他に身寄りもないそうだし。子供に罪はないからね」
俺は兄を見た。
それはいけない、と俺は思った。父は、城に置いたままにした弟に殺されかけたのだ。
ほんの少しの間、俺は逡巡した。やがて、
「俺が、連れて行く」
兄が驚いたように目を上げた。
「それは……」
「いや、兄貴が何と言おうと、俺が連れて行く」
俺が傍について育ててやれば、きっと父親のことを耳に入れずに済むだろう。そうすれば、この連鎖を断ち切ることができるに違いない。
兄はじっと俺を見つめていた。やがて、俯いて小さく息を吐いた。
「わかった。お前に頼もう」
子供は、俺を見上げて震えていた。
***
<フィガロ城 王の間> ―――マシアス王子の手記に非ず
乾ききった夏の砂漠の上、子供の手を引いて去っていく弟の背を、エドガーはずっと見送っていた。あの子を連れて行く以上、あいつは二度とここへは戻らないだろう――彼はそう思った。
「いいのか?」
ロックもその隣で二人の人影を見守りながら、そう尋ねた。
「ああ、いいさ」
エドガーはくすりと笑った。
「ロック。帰って早々悪いが、また頼みたいことがあるんだ」
「勘弁しろよ〜。新婚だぜ?」
ロックが肩を竦めると、エドガーはまたくすりと笑った。
「急かしはしないさ。今度は、スパンの長い仕事になりそうなんだ」
「……黒幕か」
「ああ」
その声色に、旧知の友人が強い決意を胸に置いたことを、ロックは悟った。
「知らぬが仏って言うぜ?」
そう言って、ロックは砂の混じった風に目を瞬かせ、部屋へ戻った。
エドガーはそれを確かめると、風除けのためのマントを体に巻き直す。
二つの人影は、蜃気楼の向こうにもうほとんど見えなくなっていた。
それでも、エドガーは弟の去っていった方角を見つめ続けた。
いつか、こんな風に暑い夏の日。
お前の育てたその子が、きっと俺を殺しに来るだろう。
でも、そんな終わり方もまたいいじゃないか?
そう。全ては運命なのだから。
-Fin-
 BACK BACK  Novels Novels  TOP TOP
|